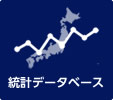エリザベス女王の逝去で英国競馬界は最良の友を失う(イギリス)【開催・運営】
9月8日(木)、英連邦をはじめ世界中の人々が喪失感を覚えただけではない。エリザベス女王陛下の死は英国競馬界にも虚無感をもたらした。競馬というスポーツは、長年にわたる熱狂的なサポーターだけでなく最良の友も失ったのだ。
英国の競馬場が女王の笑顔を迎えることはもうない。ロイヤルアスコット開催の馬車に、1953年以来いつも臨席してきた君主が現れることはもうない。そして王室の勝負服は、すっかり競馬のとりこになっていた女王陛下を象徴するものではなくなってしまった。これらのイメージが薄れるにはまだ数年かかりそうだ。
女王にとって競馬は多面的な娯楽だった。サラブレッドを生産する中で、女王の専門知識は、王室の歴史家たちが断言するように、歴代の君主(ダービーを3勝した曾祖父エドワード7世、"名種牡馬オールドローリー"とのあだ名が付けられたチャールズ2世など)を凌ぐものだったとされている。
女王は走っている馬をご覧になることで、公務の厳粛さの中で彼方へと奪い去られた自らの気持ちを表す自由を見いだされた。そして形式張らない競馬場での日々を大いに楽しまれた。そこではやんちゃな調教師たちの無邪気さをひそかに楽しむ温厚な女性校長のような存在でいられた。ふだん彼女が生きている世界とは別世界だった。
だからこそ、女王が毎日読まれていた本紙(レーシングポスト紙)の中で、そのご愛顧を称えなければならないのだ。女王は競馬界の顔であり、最強の擁護者であり、活気ある鼓動だった。それらは時とともに消散するのかもしれないが、彼女は臣民たちに身近な形で授けてくれたのだ。競馬場は、宮殿で家族が内々に見ていたような彼女の姿を映し出す唯一の公的な場所だった。いつも笑顔でくつろいでいる姿は彼女の最も人間的な肖像だった。
女王と競馬の共生関係は細部にまで至っていた。幼少期から馬に親しんできた女王は、ホースマンたちとも親交があった。馬が王である馬王国では誰もが平等である。この範疇で、女王陛下は馬主・調教師・騎手・厩務員など同じ考えをもつ人たちと交流し続けた。
馬はファンのあいだに共感を呼び起こすものである。そういうこともあり、女王陛下の競馬人生を如実に物語る数々のユーモラスな逸話の中から個人的に好きなものを1つ挙げよう。1999年にリチャード・ハノン調教師(父)の厩舎を初めて訪れたとき、女王はある乗り役にすぐ気がつかれた。ハノン調教師から、「ベティ・ブリスター氏と面識がおありですか?」と聞かれた女王は、ブリスター氏はかつて愛馬ハイクレアを世話してくれたと答えられた。この乗り役とは実に25年ぶりのご再会だった。
ハイクレアが活躍していたころ、ブリスター氏は女王の愛馬の多くを管理した偉大なディック・ハーン調教師のもとで働いていた。また、ハーン厩舎には遠征担当厩務員長のバスター・ハスラム氏がいた。女王が1977年のシルバージュビリー(即位25周年)に競馬関係者のために開かれたパーティーに彼は出席していた。後にハスラム氏が自ら命を絶った際には、女王陛下は遺族にお悔みの私信をしたためられた。
英国競馬界だけでなく世界中の競馬界が女王の死を悼んでいる。アスコットのクイーンエリザベス2世S(G1)は女王にちなんで名づけられたレースの1つである。豪州・カナダ・香港・日本・シンガポール・米国でもエリザベス女王の名をもつレースが開催されている。
女王が勝利も敗北も同じように潔く受け入れられていたことが何よりも印象深い思い出だろう。とりわけ即位してから最初の10年間は多くの勝利に恵まれたが、その時期でさえも彼女には不運な馬主としての評判が定着していった。
この不運は、女王の調教師団の1人、セシル・ボイド-ロックフォート調教師が1957年の時点ですでに認識していた。ボイド-ロックフォート調教師はレース後にハリー・カー騎手が女王のアルメリアについて前向きな報告をしたとたん、「お願いだから、女王に言わないでくれ。そんなことを言ったら、いつも何かが狂ってしまう」と懇願したのだ。
しかし1953年6月2日、戴冠式当日の朝、まもなく女王になるエリザベス王女が述べられた最後の言葉の1つは次のようなものである。侍女に"お気持ちはいかがですか?"と聞かれた彼女は"最高です"と答えられた。ボイド-ロックフォート調教師がダービー出走を4日後に控えた愛馬オリオールが素晴らしい最終追い切りを行い準備万端だと知らせる電話を掛けてきたとおっしゃるのだ。
ダービーデーがやってきて、オリオールは2着に甘んじた。しかし、人々に愛される彼の馬主のことを、同じように一番でないなどと言うような人はどこにも存在しないだろう。
By Julian Muscat
[Racing Post 2022年9月8日「The Queen was racing's public face, its strongest advocate, its vibrant pulse」]